こんにちは。
「カムカム・シンセサイザー」ブログの管理人のKAMINです。
プロフィールに自分のブログに対する思いを書きましたが、今は所有していませんが、どんな経緯でシンセサイザーを購入してきたか、思い出とともに書き綴ってみたいと思います。

今ではほとんど手放してKORG microKORG XL+と音源モジュールのRoland JD-990、ドラム音源モジュールのALESIS D4。そして最近購入したKORG opsixしかありませんが、若い自分がシンセサイザーの進化とともにどのような経緯で購入してきたか、参考になればと思って書きます。
Roland SYSTEM-100M
小学生からTVで音楽を聴くのが大好きで、中学1年の冬にフォークギターを購入。
それを見ていた親父が渡してくれたのが「ロッキンf」(笑)
キッスやクイーンは知っていたけれど、ハードロックはちっともわからん。
そんな中でシンセサイザーの記事があったんだ。
冨田勲さんや喜多郎さん、ミッキー吉野さん、深町純さんは知っていたので、「これがシンセサイザーなんだ」と写真を見てうずうずしていた。
中学3年生になるとYMOが流行ったりして、シンセサイザーが少し認知され始めたんだ。
高校の入学祝と貯金をはたいて買った。
中学の時に月1回、秋葉原に行く用事があって、他に電気部に入部していたから秋葉原にはよく行ったな。
当時、LAOX(懐かしい!)へ行くとシンセサイザーがたくさんあった。
KORG PS-3300にPS-3100、国産メーカーのモノフォニック・シンセサイザーは一通りあったんじゃないかな。
で、触る人はほとんどいない(笑)
テープ・エコーもあったし、KORGのロータリー・スピーカーもあった。
試奏もできて、ヘッドフォンで音を確認できた。
Rolandのショールームもあって、何度か足を運んだ。
SYSTEM-700が鎮座していたのを横目で見ながら、試奏コーナーでヘッドフォンつけていじってました。
そんなことから親父の車に乗って秋葉原のLAOXへ。
何故か購入すると鍵盤が少ないモジュールが付いていた。
「このモジュールをつけないとどのくらい安くなります?」と交渉したら3千円。
なので付けてもらって購入。
これとCUBE-40(キーボード・アンプ)とコードとヘッドフォン。
私はというと、ワクワクしながらパッチ・ワーク。
Rolandのショールームに行っていたから、シンセサイザーの知識はあったんだ。
一度、会員でもないのに会員の「はじまるよ」の声に椅子に座って講習会を受けてしまったり(笑)
その時に使っていたのがRoland SYSTEM-100Mだった。
これが購入理由。
音が出れば、「うん、うん、これだっ!」と言いながら、「あと何ができるの?」、「全然、TOMITAサウンドにならないじゃんっ。」とか(笑)
ある日、親父が弾いてみたいと言うんで貸したが、ヘッドフォンで指一本で弾いていた。
「何弾いているの?」と聞いたら、「学校の校歌」だって(笑)
親父はサービスでもらった鍵盤モジュールに音階をシールで貼っていた。
几帳面な性格。
もちろん、親父はA型です(笑)
エフェクターのない状況でシンセサイザーの音を聴くとぶっとい音。
そんな中、高校の友達とその仲間たちで演奏会を開こうということになって、友達が谷村新司の「終止符」を歌うんで、イントロのヴァイオリンの音をシンセサイザーの音で鳴らしてほしいと頼まれた。
単純なんで演奏したが、LFOで「うにょうにょ」した音になっっちゃった。
それが最初で最後のライブでのシンセサイザー演奏のお披露目(笑)
冷や汗というのはこういう時にかくんだね(笑)
この時は手作りの演奏会。
練習場は私の住んでいたアパートの空き部屋か公民館。
自分たちで御苑スタジオまで行ってマイクやスタンド等の機材を借りて当日設営。
雨の中、友達が来てくれて嬉しかったよ。
こんな思い出のあるシンセサイザーも、高校卒業後にエレクトリック・アコースティック・ギターが欲しくて下取りに出したんだな。
KORG Δ
Roland SYSTEM-100Mはモノフォニック・シンセサイザーでしょ。
やっぱり和音が欲しいよね。
で、KORG Δを購入。
使える出音は、、、ほぼオルガンとストリングス(笑)
ストリングスは気持ちよかったよ。
ヘッドフォンでしか使えなかった環境で結構ノイズがのってしまって、気が引けてしまったんだ。
でも、ライブでキーボードを弾くメンバーに貸したり、高校のOBの先輩に貸したり、私以外の人に重宝されたものです。
シンセサイザーって当時はまだ普及していないが、巷に流れる音楽には使われ始めていて、バンドをする人にとっては貴重なアイテムだったんだ。
だって1980年代初めのアマチュア・バンドがストリングスの音をバンドで使うなんてハイカラでしたでしょ。
当時ギターばかり弾いていた自分としては、キーボードを使って演奏することには、あまり興味がなかった。
YAMAHA DX-7
時代の波は、浪人中に起こった。
1983年、DX-7の登場。
翌年バイトして購入したよ。
新宿の石橋楽器へ電車で行って購入。
ハード・ケースも購入して、、、徒歩で行ったから、徒歩で帰るんだけれど、最寄りの駅は新宿三丁目。
地下鉄は階段があるから一駅だけなので新宿駅まで重たい思いをして、何度も持ち手を替えてひたすら歩く。
酔っぱらった様子のつのだ☆ひろさんを見かけたが、見向きもせずにただひたすら歩く、歩く...
当時、埼玉県川口市に住んでいたので、その道のりは長かった。
池袋駅で乗り換え、赤羽駅で乗り換え。
当時の赤羽駅はエスカレーターがなかったからね。
階段を下って地下道を歩いてまた昇る。
そして、川口駅へ着いてから徒歩15分。
DX-7は本体だけで20kg。ハードケース付きだと...もっと重い。
持ち運びするシンセを選ぶなら、軽いタイプを選ばないとね。
でも、あの音は衝撃的だった。
エフェクトなしでも気持ちよかった。
バンドで演奏。
当時THE SQUAREが流行っていたから、リリコン代わりにDX-7にブレス・コントローラーを付けて演奏。
そのためにエディットしたな。
キーボードを弾けなくても何とかなった(笑)
でも、ライブとかのお披露目はなし。
SEQUENTIAL CIRCUITS Prophet-5
会社員となり、2年目のボーナスもらって、購入を決意。
もう、夢の楽器。
下北沢のANDY’S MUSICまで親父と行って、駐車場に待たせて、中古を購入。
ジェラルミン・ケースに入れられたシンセを、シビックの後部座席に入れて、持ち帰り。
出音が楽しいのなんのって。
一番ウキウキできたシンセ。
エフェクターをかけなくても気持ちよいっ! エフェクターかけるとまた気持ちよい(笑)
KORG 01/W
このころになると、ワークステーション・シンセサイザーに注目が集まっていた。
KORG M1がバカ売れしていたからね。
そんな中、01/Wを購入。
ウェーブ・シャイピングって新機能があったけれど、レベルを上げるとデジタル・ノイズまみれになるといった印象しかなかった。
オルガンの音とかストリングスの音とか、「PCM音源」ってこうなんだな、と。
エディットは、パラメーターを一つ選んで、VALUEキーを上げ下げ。
そのうちにエディットする気が萎えてしまった。
Roland JD-990
01/Wがあるので、音源モジュールで違うタイプの音が出せるものを物色。
デジタル・シンセサイザーでモジュール音源。
VALUEのノブが付いていて、LEDで複数のパラメーターが表示できて、本体でも何とかエディットできそう。
そして、決め手はエクスパンド・モジュール(VINTAGE SYNTH)。
往年のビンテージ・シンセサイザーの波形が入っているボードを指すと、いろんなメーカーの音が楽しめる。
これをPCのサウンド・エディターでいじる。
PCはMacの「Performer 588」。
Mark of the Unicorn「Unysin」というサウンド・ライブラリアン&エディターを使っていた。
「うーん、そうそう、あの音色だ」といった感じ。
これはもうワクワクしていじっていた。
同じ波形でもメーカーによって違うってことが実感できた機材だから、これだけは未だに自分の手元に置いてある。
今のシンセサイザーはメモリーに余裕があって、Rolandやいろんなメーカーから当時はやった音の波形はどっさり組み込んだ機種がいっぱいあるから、他の人にはそんなに愛着がないかもしれない。
これから購入する方は音色が多すぎて選ぶのに困るほどだよね。
YAMAHA MU-80
マルチ音源が欲しかった。
Roland JD-990があったから、XG音源でということでYAMAHA MU-80を購入。
E-MU Proteusが発売されていたんですが、そこまで高くなくてもいいやと判断したんだ。
EFFECTORも入っていたし、アマチュアの多重録音環境には申し分なしだった。
Waldolf micro wave
ここまでくると外国のメーカーの音が欲しいよね。
これは四人囃子の再結成ライブで坂本秀美さんがWaldolfの前身のPPGを弾いていた。
あと、ProphetONEとか。
ライブのビデオを見ながら、「ちょっと違うぞ、このシンセ」と思って、その流れを汲んだWaldolf micro waveを購入。
ENSONIQ(VFXだったかな?)と悩んだけれど、Waldolfのウェーブ・テーブルに手を出した。
音源モジュールで音色の変化に魅了されたんだ。
いじっているうちに訳がわからなくなる(笑)
その後は、PCソフトのライブラリアン&エディターソフトのUnysinでランダマイズして遊ぶ(笑)
当時からランダマイズ機能はソフトではあったんだ。
シンセサイザーで遊ぶには面白い機能だよ。
まとめ
私の場合、当時のシンセサイザーの技術の進化に翻弄されながら、アマチュアとしてシンセサイザーを購入していったという感じです。
ポリフォニック・シンセサイザーが安価になってきてから購入し始めた人がちらほら出てきていたと思います。
当時シンセサイザーからキーボードを弾くようになった人は見かけませんでした。
バンドで演奏する人は「ピアノが弾ける人」に使ってもらうように、シンセサイザーを知っている人が教えて使ってもらうって感じでした。
PCM音源のシンセサイザーが販売されて、キーボードが安価になったころで一気に普及した。
アイドルや流行のバンドの楽曲はシンセサイザーの音が大半を占めている状況になって、みんなが注目し始めたんだ。
1990年代からは楽器屋さんのキーボード・コーナーがどんどん増えていた感じでした。
その頃には社会人になって購入できるが遊ぶ時間がなくなってしまったんだな。
そのうちに自分の興味は知り合いのライブに足を運ぶことに夢中になってしまって...
そしてアマチュアのオープン・マイクでギター弾いたり、新たにマンドリンに興味を持ったり...
20年以上、集中してシンセサイザーを楽しむことがなくなっていたんだ。
その後、このブログを立ち上げる経緯は「シンセサイザーに再び目覚めたきっかけ」に書いた記事の通りです。
この記事を読んだ方がシンセサイザーに興味を持っていただけたら幸いです。
では。
↓このブログは、「にほんブログ村」に参加しています↓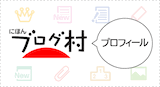
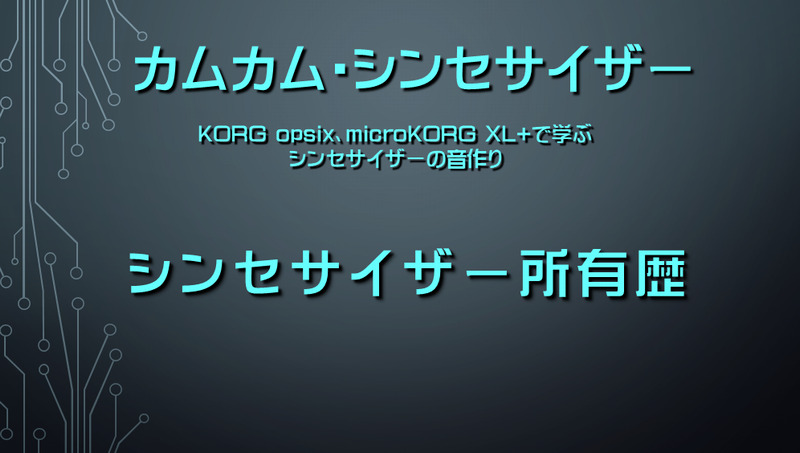

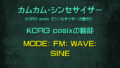
コメント