みなさん、こんにちは。
「カムカム・シンセサイザー」のKAMINです。
このブログではシンセサイザーの基本構成から機能まで、microKORG XL+のSound Editorを用いて実験しながらイメージと音データを使って説明しています。
そして、新たにFMシンセサイザーのKORG opsix、opsix nativeの機能や使い方の記事を順次掲載しております。
下のボーダー・タイトルをクリックすると一覧が表示されますので、ご興味のある記事からご覧ください。
最新の投稿記事
- KORG opsixのプリセット分析: 262 Hard Synkronicity
- KORG opsixのプリセット分析: 200 Feel The Warmth
- KORG opsixのプリセット分析: 202 Engagement Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 192 Breezy Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 002 Original FM EP
opsix、opsix nativeの記事


ボーダー・タイトルをクリックすると、記事一覧が表示されます。
- KORG opsix、opsix nativeを同時購入しました
- KORG opsix、opsix nativeを3か月間使って分かったこと
- KORG opsix、opsix nativeを3か月間使って分かった利用用途の違い
- シンセサイザーのFMの本はこれ一択です。
- KAMINのFM音源への想い
- KORG opsix SE(Platinum)の魅力
- [ハード編] KORG opsix、opsix nativeの進化版を考えてみた
- [サウンド・エンジン編] KORG opsix、opsix nativeの進化版を考えてみた
- [opsix native編] KORG opsix、opsix nativeの進化版を考えてみた
- KORG opsix mk II、opsix moduleが発売されました
1つ1つパラメーターを絞って使ってみるとKORGの技術に
「よくぞやってくれました!」と感嘆させられることがあります。
なんでもっと宣伝しないんだろうと思うところもありますね。
半面、「もっとこうして欲しい」といった贅沢な悩みも出てきます(笑)

opsix、opsix nativeを同時購入に至った経緯、
使ってみた感想等を書いています。
KORG opsix、opsix nativeの同時購入、環境構築の流れ
- KORG opsixを購入後に設定すること(PC接続時の設定)
- KORG opsix Sound Librarianのインストール
- KORG opsixのVersion2.0へのアップデート
- KORG opsix nativeの購入(opsixのクロスグレード)
- KORG opsix nativeのインストールデータの入手手順
- KORG opsix nativeのインストールと環境設定手順
- KORG opsixとopsix nativeのPROGRAMデータのやりとり
イメージを掲載してわかりやすく手順を説明しています。

opsix、opsix nativeの同時購入からopsixのバージョン2.0へのアップデート、
クロスグレードしたopsix nativeの購入手順からインストール、
PC環境の設定手順まで説明しています。
- KORG opsixの機能の説明と実験方法
- KORG opsixの構成
- KORG opsixのページ・グループとページ
- KORG opsixのパラメーターで使われる単位
- KORG opsixの機能: INIT(初期設定)プログラムの分析
- KORG opsix: 実験時の設定
- KORG opsixの機能: HOME/ALGOページ・グループ
- KORG opsixの機能: FMのオペレーターとアルゴリズム
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(1)
- RATIO: OP1(C): 1.0000、OP2(M): 1.0000での実験
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(2)
- RATIO: OP1(C): 1.0000、OP2(M): 2.0000での実験
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(3)
- RATIO: OP1(C): 1.0000、OP2(M): 5.0000での実験
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(4)
- RATIO: OP1(C): 20.0000、OP2(M): 1.0000での実験
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(5)
- RATIO: OP1(C): 1.0000、OP2(M): 0.5000での実験
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(6)
- キャリアに固定周波数設定のFIXEDを用いて実験
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(7)
- 3段以上のオペレーターでの直列接続
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(8)
- Y字接続(キャリアに対してモジュレーターが並列接続する組み合わせ)
- KORG opsixの機能: FMのキャリアとモジュレーターの関係(9)
- 逆Y字接続(2つのキャリアに対してモジュレーターが1つで並列接続する組み合わせ)
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 327 [TMP] 2OP FM
- KORG opsixの機能: MODEページ・グループ
- KORG opsixの機能: MODE: FM
- KORG opsix: WAVEFORM LIST
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE
- opsixの波形を音と画像で確認します。
- MODE: FM: WAVE: のページは比較できるように波形単位で同じ実験をしています。
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SINE
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SINE 12BIT
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SINE 8BIT
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: TRIANGLE
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SAW
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SAW HD
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SQUARE
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: SQUARE HD
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE SAW3
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE SQUARE3
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE TRIANGLE3
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 12345
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+2
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+3
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+4
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+5
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+6
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+7
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: ADDITIVE 1+8
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: NOISE S/H
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: NOISE WHITE
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: NOISE PINK
- KORG opsixの機能: MODE: FM: WAVE: NOISE BLUE
- KORG opsixの機能: MODE: RING
- KORG opsixの機能: MODE: RING: DEPTH
- KORG opsixの機能: MODE: RING: SHAPE
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 331 [TMP] Ring Mod
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER: TYPE
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER: CUTOFF
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER: RESONANCE
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 324 [TMP] Reso Noise
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER FM
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER FM: CUTOFF
- KORG opsixの機能: MODE: FILTER FM: RESONANCE
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 335 [TMP] Filter FM
- KORG opsixの機能: MODE: WAVE FOLDER
- KORG opsixの機能: MODE: WAVE FOLDER: GAIN
- KORG opsixの機能: MODE: WAVE FOLDER: OSC MIX
- KORG opsixの機能: MODE: WAVE FOLDER: BIAS
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 334: [TMP] Wavefolder
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: PEAKING EQ
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 020: Ana Eleki Piano
- KORG opsix: MODE: EFFECT: SHELVING EQ
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 102 Angklung Lore
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: PHASER
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 340 [TMP] Phaser Noise
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: SHORT DELAY
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 337 [TMP] Delay Mod
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: COMB FILTER
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 338 [TMP] Comb Flanger
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: DISTORTION
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 238 Thick Screamer
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: DRIVE
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 339 [TMP] Comb LFO
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: DECIMATOR
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 033 Folk Piano
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER(TYPE: 00-09)
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER(TYPE: 10-19)
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER(TYPE: 20-29)
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER(TYPE: 30-39)
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER(TYPE: 40-49)
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER(TYPE: 50-59)
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER: OSC MIX
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: WAVESHAPER: DAMP
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 336 [TMP] Waveshape
- KORG opsixの機能: MODE: EFFECT: PUNCH
- KORG opsixのプリセット音のパラメーター分析: 009 Punchy Wire Piano
- KORG opsixの機能: MODE: BYPASS、MODE: MUTE
- KORG opsixの機能: PITCHページ・グループ
- KORG opsixの機能: PITCH: FREQUENCY MODE
- KORG opsixの機能: PITCH: TRANSPOSE
- KORG opsixの機能: PITCH: DETUNE
- KORG opsixの機能: P MOD: EG1
- KORG opsixの機能: P MOD: LFO1
- KORG opsixの機能: P MOD: VELOCITY
- KORG opsixの機能: LEVEL/EGページ・グループ
- KORG opsixの機能: EGページ
- KORG opsixの機能: EG: ATTACK TIME
- KORG opsixの機能: EG: DECAY TIME
- KORG opsixの機能: EG: SUSTAIN LEVEL
- KORG opsixの機能: EG: RELEASE TIME
- KORG opsixの機能: EG: CURVE、LEVEL
- KORG opsixの機能: KEY TRACKページ
- KORG opsixの機能: L MODページ
- KORG opsixの機能: MODページ・グループ
- KORG opsixの機能: MOD: EG: CURVE
- KORG opsixの機能: MOD: LFO: WAVE
- KORG opsixの機能: MOD: LFO: SPEED
- KORG opsixの機能: MOD: LFO: KEY SYNC
- KORG opsixの機能: MOD: LFO: TEMPO SYNC
- KORG opsixの機能: MOD: LFO: PHASE
- KORG opsixの機能: MOD: LFO: FADE
- KORG opsixの機能: EFFECTページ・グループ
- KORG opsixの機能: EFFECT実験時の基本設定
- KORG opsixのエフェクター: CHORUS
- KORG opsixのエフェクター: UNISON ENSEMBLE
- KORG opsixのエフェクター: PHASER
- KORG opsixのエフェクター: PHASER(BPM)
- KORG opsixのエフェクター: AUTO PAN
- KORG opsixのエフェクター: AUTO PAN(BPM)
- KORG opsixのエフェクター: FLANGER
- KORG opsixのエフェクター: FLANGER(BPM)
- KORG opsixのエフェクター: ROTARY SPEARKER
- KORG opsixのエフェクター: AUTO WAH
- KORG opsixのエフェクター: EXCITER
- KORG opsixのエフェクター: ENHANCER
- KORG opsixのエフェクター: LFO FILTER
- KORG opsixのエフェクター: 3-BAND EQ
- KORG opsixのエフェクター: DISTORTION
- KORG opsixのエフェクター: GUITAR AMP
- KORG opsixのエフェクター: DECIMATOR
- KORG opsixのエフェクター: GRAIN SHIFTER
- KORG opsixのエフェクター: MASTER LIMITER
- KORG opsixのエフェクター: COMPRESSOR
- KORG opsixのエフェクター: DELAY
- KORG opsixのエフェクター: DELAY(BPM)
- KORG opsixのエフェクター: AUTOPAN DELAY
- KORG opsixのエフェクター: AUTOPAN DELAY(BPM)
- KORG opsixのエフェクター: TAPE ECHO
- KORG opsixのエフェクター: TAPE ECHO(BPM)
- KORG opsixのエフェクター: EARLY REFLECTION
- KORG opsixのエフェクター: REVERB
- KORG opsixのエフェクター: SHIMMER REVERB
- KORG opsixのエフェクター: SPRING REVERB
- KORG opsixの機能: VOICEページ・グループ
- KORG opsixの機能: VOICE: ASSIGN
- KORG opsixの機能: VOICE: GLIDE
- KORG opsixの機能: VOICE: UNISON
- KORG opsixの機能: VOICE: DETUNE
- KORG opsixの機能: VOICE: SPREAD
- KORG opsixの機能: MISCページ・グループ
- KORG opsixの機能: MISC: PROG PITCHページ
- KORG opsixの機能: MISC: PROG MISCページ
- KORG opsixの機能: MISC: USER ALGページ
- KORG opsixの機能: MISC: OP UTIL ページ
- KORG opsix: CONTROL SOURCE LIST
- KORG opsix: VIRTUAL PATCH SOURCE LIST
- KORG opsix: VIRTUAL PATCH DESTINATION LIST
- KORG opsix: MOTION DESTINATION LIST
記事には、opsixとopsix nativeの画面、実験時の設定値、音データ、波形、
周波数スペクトルのイメージで機能や使い方をわかりやすく説明しています。

opsix、opsix nativeの機能や使い方について、パラメーターごとに
音と画像を交えながら詳しく説明します。
- KORG opsixの機能: INIT(初期設定)プログラムの分析
- KORG opsixのプリセット分析: 327 [TMP] 2OP FM
- KORG opsixのプリセット分析: 331 [TMP] Ring Mod
- KORG opsixのプリセット分析: 324 [TMP] Reso Noise
- KORG opsixのプリセット分析: 335 [TMP] Filter FM
- KORG opsixのプリセット分析: 334: [TMP] Wavefolder
- KORG opsixのプリセット分析: 020: Ana Eleki Piano
- KORG opsixのプリセット分析: 102 Angklung Lore
- KORG opsixのプリセット分析: 340 [TMP] Phaser Noise
- KORG opsixのプリセット分析: 337 [TMP] Delay Mod
- KORG opsixのプリセット分析: 338 [TMP] Comb Flanger
- KORG opsixのプリセット分析: 238 Thick Screamer
- KORG opsixのプリセット分析: 339 [TMP] Comb LFO
- KORG opsixのプリセット分析: 033 Folk Piano
- KORG opsixのプリセット分析: 336 [TMP] Waveshape
- KORG opsixのプリセット分析: 009 Punchy Wire Piano
- KORG opsixのプリセット分析: 057 Strum Down
- KORG opsixのプリセット分析: 134 Ring It On
- KORG opsixのプリセット分析: 178 Formant Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 157 FilterFM Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 024 Dynamik
- KORG opsixのプリセット分析: 240 Dirty Trautonium
- KORG opsixのプリセット分析: 311 KONG’s Footstep
- KORG opsixのプリセット分析: 087 Snow Ball
- KORG opsixのプリセット分析: 022 Comb Piano
- KORG opsixのプリセット分析: 314 Delay Modulator
- KORG opsixのプリセット分析: 266 Purple Dist EG
- KORG opsixのプリセット分析: 237 Cinematic FB Doom
- KORG opsixのプリセット分析: 313 Cockpit Emergency
- KORG opsixのプリセット分析: 007 Waveshape EP
- KORG opsixのプリセット分析: 086 FM Airy Bell
- KORG opsixのプリセット分析: 269 Arp Swirls
- KORG opsixのプリセット分析: 270 ARP Flurry
- KORG opsixのプリセット分析: 011 FM Vamp
- KORG opsixのプリセット分析: 035 Comb Dulcimer
- KORG opsixのプリセット分析: 062 FMarimba
- KORG opsixのプリセット分析: 082 MIDI Stack
- KORG opsixのプリセット分析: 222 Jazz Bass
- KORG opsixのプリセット分析: 241 Mod Saw Lead
- KORG opsixのプリセット分析: 212 Laid Bass
- KORG opsixのプリセット分析: 189 Pad Mod Fizz
- KORG opsixのプリセット分析: 250 Theremax
- KORG opsixのプリセット分析: 001 Dat Electric Piano
- KORG opsixのプリセット分析: 026 Portrait EP
- KORG opsixのプリセット分析: 121 Filtered Saws
- KORG opsixのプリセット分析: 095 FM Wind Chime
- KORG opsixのプリセット分析: 122 Franalog
- KORG opsixのプリセット分析: 127 Inspirational Story
- KORG opsixのプリセット分析: 017 Roads and Roads
- KORG opsixのプリセット分析: 302 Hardgroove
- KORG opsixのプリセット分析: 205 Glass Waves
- KORG opsixのプリセット分析: 233 Spread Love
- KORG opsixのプリセット分析: 273 Deli Arp
- KORG opsixのプリセット分析: 015 Overcompressed
- KORG opsixのプリセット分析: 030 Mutated Piano
- KORG opsixのプリセット分析: 032 Unsteady
- KORG opsixのプリセット分析: 037 Metalic Pluck
- KORG opsixのプリセット分析: 042 Wave Shaper Clav
- KORG opsixのプリセット分析: 043 Pulse Clav
- KORG opsixのプリセット分析: 045 DrawSlider Organ
- KORG opsixのプリセット分析: 046 Tone Wheel Organ
- KORG opsixのプリセット分析: 063 Membrane Pluck
- KORG opsixのプリセット分析: 065 4 Tap Diffusion
- KORG opsixのプリセット分析: 072 Crystal Syn Bell
- KORG opsixのプリセット分析: 073 Maverick Bells
- KORG opsixのプリセット分析: 075 Percussion
- KORG opsixのプリセット分析: 079 Crystal Bells
- KORG opsixのプリセット分析: 108 Spinners
- KORG opsixのプリセット分析: 112 Fairy Tweets
- KORG opsixのプリセット分析: 144 Slight Touch
- KORG opsixのプリセット分析: 150 FM Ring Mod Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 173 Star Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 184 opsix Concrete
- KORG opsixのプリセット分析: 208 Punchy SynBass
- KORG opsixのプリセット分析: 211 Funk Bass
- KORG opsixのプリセット分析: 216 Aphasin Bass
- KORG opsixのプリセット分析: 220 Analog=FM Bass
- KORG opsixのプリセット分析: 280 Algo Tripping MW
- KORG opsixのプリセット分析: 290 WS Pulse Anthem
- KORG opsixのプリセット分析: 050 Ring Pipe Organ
- KORG opsixのプリセット分析: 099 Pluck Drip
- KORG opsixのプリセット分析: 147 Wasps
- KORG opsixのプリセット分析: 041 MW Phasing Clav
- KORG opsixのプリセット分析: 051 Glide Sine
- KORG opsixのプリセット分析: 093 Plinq Plunq
- KORG opsixのプリセット分析: 010 Just Hang On
- KORG opsixのプリセット分析: 232 Sub’n Pluck
- KORG opsixのプリセット分析: 055 Bright Plectrum
- KORG opsixのプリセット分析: 089 Ruin Chatters
- KORG opsixのプリセット分析: 039 Reso Phase Clav
- KORG opsixのプリセット分析: 293 Quadratic Chord Pulse
- KORG opsixのプリセット分析: 228 FLDR Bass
- KORG opsixのプリセット分析: 107 MOD Storm
- KORG opsixのプリセット分析: 109 Shifting 9th
- KORG opsixのプリセット分析: 038 Metaklav
- KORG opsixのプリセット分析: 091 Night Sky
- KORG opsixのプリセット分析: 161 Quiet Motion
- KORG opsixのプリセット分析: 242 Xover Bright Lead
- KORG opsixのプリセット分析: 230 Ven aqui ya
- KORG opsixのプリセット分析: 199 Simple PWM
- KORG opsixのプリセット分析: 002 Original FM EP
- KORG opsixのプリセット分析: 192 Breezy Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 202 Engagement Pad
- KORG opsixのプリセット分析: 200 Feel The Warmth
- KORG opsixのプリセット分析: 262 Hard Synkronicity
プログラムの分析として各パラメーターのINITプログラムとの違いを
実験時の設定値、音データ、波形、周波数スペクトルのイメージで
機能や使い方をわかりやすく説明しています。

プリセット音を分析してみると、プロのプログラマーの凄さがわかります。
そのテクニックを自分の音作りに活かしていきましょう。(順次更新中)
microKORG XL+の記事
このブログでは、KORG microKorg XL+のSound Editor画面を使って説明しています。

- microKORGとmicroKORG XL+、どちらがいいの?
- microKORG XL+のプリセット音は大人しい?
- microKORG XL+の取扱説明書はわかりやすい
- microKORG XL+は音作りを学ぶ人にとっておすすめです
ロングセラーなシンセサイザーには機能的な面以外にもいろいろな点で良さがあります。
Sound Editorを使用できるPCをお持ちの方ならmicroKORG XL+は
音作りをするシンセサイザーとしてお勧めします。
幾つかのモデルが登場しているので、その違いも含めて紹介しています。

microKORG XL+はシンセサイザーを学ぶ人にとっての
おすすめポイントを説明しています。
- ~1970年代従来のアナログ・シンセサイザーの機能
モノフォニック(単音)だったころの基本機能
- オシレーター:OSCILLATOR
- フィルター:FILTER
- フィルターの効果(1)
- フィルターの効果(2)
- フィルターの効果(3)
- アンプとエンベロープ・ジェネレーター:AMP、AMP EG(EG2)
- フィルターによる時間的変化:FILTER EG(EG1)
- 音の周期的な変化:LFO(1)
- 音の周期的な変化:LFO(2)
- 音の周期的な変化:LFO(3)
- 音域による音の変化:KEY TRACK
- 次の音に移行する時間を自動コントロール:PORTAMENT
- 音の高さを調節する:TRANSPOSE、DETUNE
- コントローラー:[ピッチ]ホイール、[MOD]ホイール
複数のオシレーターによる音作り
- 1980年頃ポリフォニック化、ステレオ化
- 音の強弱
ベロシティ
- デジタル化
デジタル化で追加された機能(KORG独自の機能を含む)
- デジタル化で追加された機能(0)概要
- デジタル化で追加された機能(1)OSC <1>
「フォルマント波形、PCM/DWGS波形」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <2>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:SAW、OSC1 MOD:WAVEFORMでの
C1:WAVEFORM)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <3>
OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:PULSE、OSC1 MOD:WAVEFORMでのC1:
PULSE WIDTH)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <4>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:TRIANGLE、OSC1 MOD:WAVEFORMでの
C1:WAVEFORM)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <5>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係(WAVE:SINE、OSC1 MOD:WAVEFORMでのC1:WAVE SHAPE)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <6>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:SAW/PULSE/TRIANGLE、
OSC1 MOD:WAVEFORMでのC2:LFO1 MOD)」と
「WAVE:SINE、OSC1 MOD:WAVEFORM、
C2:WAVE SHAPE MOD」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <7>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:SAW/PULSE/TRIANGLE/SINE、
OSC1 MOD:CROSS、C2:LFO1 MOD)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <8>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:FORMANT、OSC1 MOD:WAVEFORMでの
C1:FORMANT WIDTH)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <9>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:FORMANT、OSC1 MOD:WAVEFORMでの
C2:FORMANT SHIFT)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <10>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係(WAVE:NOISE、OSC1 MOD:WAVEFORMでのC1:RESONANCE)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <11>
「OSC1の波形とモジュレーションとコントローラーの関係
(WAVE:NOISE、OSC1 MOD:WAVEFORMでの
C2:LPF/HPF)」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <12>
「PCM/DWGS波形によるコントローラーの機能」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <13>
「OSC MOD:UNISON」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <14>
「OSC MOD:VPM」 - デジタル化で追加された機能(1)OSC <15>
「PUNCH LEVEL」 - FILTER:ROUTING - Sound Editor シンセ・エディット・
ウィンドウの表示までの操作手順 - デジタル化で追加された機能(2)FILTER <1>:FILTER:ROUTING
- デジタル化で追加された機能(2)FILTER <2>:FILTER1:
BALANCE(TYPE BALANCE) - デジタル化で追加された機能(3)DRIVE/WAVE SHAPE
- デジタル化で追加された機能(4)LFO
- デジタル化で追加された機能(5)VIRTUAL PATCH
- デジタル化で追加された機能(6)ASSIGNABLE EG(EG3)
- デジタル化で追加された機能(7)ANALOG TUNE
- デジタル化で追加された機能(8)[RANDOMIZE]ボタン
- デジタル化で追加された機能(9)
プログラム・エディット・ウィンドウのパラメーター - デジタル化で追加された機能(10)KNOB
- イコライザー:EQ
- アルペジエーター
エフェクター
- microKORG XL+のエフェクター(概要)
- microKORG XL+のエフェクター STEREO COMPRESSOR
- microKORG XL+のエフェクター STEREO FILTER
- microKORG XL+のエフェクター 4BAND EQ
- microKORG XL+のエフェクター DISTORTION
- microKORG XL+のエフェクター STEREO DECIMATOR
- microKORG XL+のエフェクター STEREO DELAY
- microKORG XL+のエフェクター L/C/R DELAY
- microKORG XL+のエフェクター STEREO AUTO PANNING DELAY
- microKORG XL+のエフェクター STEREO MODULATION DELAY
- microKORG XL+のエフェクター TAPE ECHO
- microKORG XL+のエフェクター STEREO CHORUS
- microKORG XL+のエフェクター STEREO FLANGER
- microKORG XL+のエフェクター STEREO VIBRATO
- microKORG XL+のエフェクター STEREO PHASER
- microKORG XL+のエフェクター STEREO TREMOLO
- microKORG XL+のエフェクター STEREO RING MODULATOR
- microKORG XL+のエフェクター GRAIN SHIFTER
- microKORG XL+のエフェクターを使って分かったこと
microKORG XL+の機能から、シンセサイザーのパラメーターを一つずつ説明しています。
デジタル化のOSCなんかサブ・タイトルが長くて困ったし...
なので、記事がこんなに多くなってしまいました(笑)

microKORG XL+の音、Sound Editorの画像によりシンセの機能を
時代ごとに装備された機能順に使い方を説明しています。
パラメーターのほとんどを説明しています。
エフェクトも含めて一通り実験しました。
- microKORG XL+ Sound Editorのインストール
- microKORG XL+ Sound Editor PCとの接続と本体の設定
- microKORG XL+ Sound Editorの画面構成
- microKORG XL+ Sound Editor プログラム[INITPROG]の
シンセ・エディット・ウィンドウを開く手順 - microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(ファイル)
- microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(編集)
- microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(通信)
- microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(設定)
- microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(ウィンドウ)
- microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(ヘルプ)
- microKORG XL+ Sound Editor メニュー操作(グローバル)
- microKORG XL+ Sound Editor プログラムの操作
(切り取り、コピー、貼り付け) - microKORG XL+ Sound Editor プログラムの操作(初期化)
- microKORG XL+ Sound Editor プログラムの操作
(選択プログラムの受信、書き込み) - microKORG XL+ Sound Editor プログラムの操作
(プログラム・ファイルの保存・読み込み) - microKORG XL+ Sound Editor プログラムの操作
(保存時のデータに復元) - microKORG XL+ Sound Editor ドラッグ&ドロップによる
プログラムのコピー - microKORG XL+ Sound Editor ドラッグ&ドロップによる
プログラムの移動 - microKORG XL+ Sound Editor ティンバー・データのコピー手順
- microKORG XL+ Sound Editor グローバル・ページでの操作
- microKORG XL+ Sound Editorを使ってわかったこと
Sound Editorのインストール方法から使い方まで、メニューに沿って
一通りイメージを掲載して説明しています。
マニュアルに書いてないこともいくつか書いてます。

microKORG XL+は本体にノブが少ないのですが、
Sound Editorを用いることによって、PC画面で
本体のプログラムを直接エディットできます。
インストール方法から使い方まで詳しく図解して説明しています。
- シンセサイザー 音作りの第一歩
- シンセサイザーの基本構成:音の3要素 「音の高さ」、 「音色」、 「音量」
- シンセサイザーの基本構成:音の時間的変化、音域 による変化
- シンセサイザーの基本構成:演奏時に操作するコントローラー
昔のアナログ・シンセサイザーは今と違って多機能ではなかった。
その基本構成を最初に覚えるとシンセサイザーの機能がわかりやすくなります。

シンセサイザーの基本構成を説明しています。
従来のアナログ・シンセサイザーの主な基本機能を学ぶための
基本的な内容となっています。
シンセサイザーをはじめたい方はこちらからどうぞ。

そこらにいるおじさんですが、1970年代からシンセサイザーに
興味を持って今でも好きでいられるだけの熱意はあります。
シンセサイザーだけではなく、音楽に関して興味を持ってきました。
他の方と興味のベクトル、アンテナは違うかも...(笑)
みなさんがシンセサイザーに興味を持っていただけたら、幸いです。
では。
サウンドハウスからの購入はこちらから

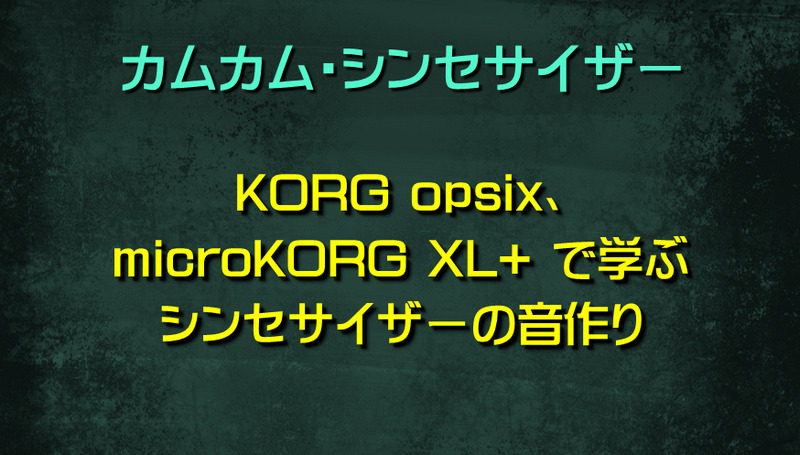





新たな進化を遂げたKORGのFMシンセサイザー、opsixとopsix native。
このブログでは、その魅力を細かく音と画像で詳しく説明していきます。